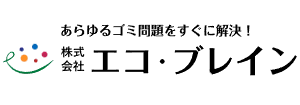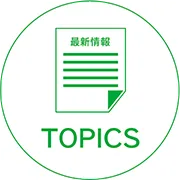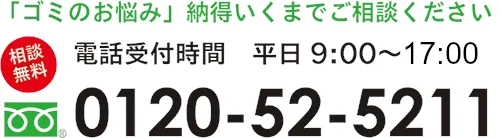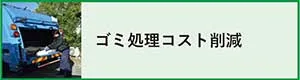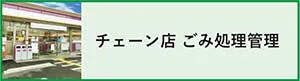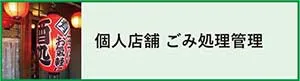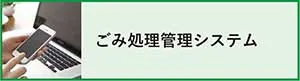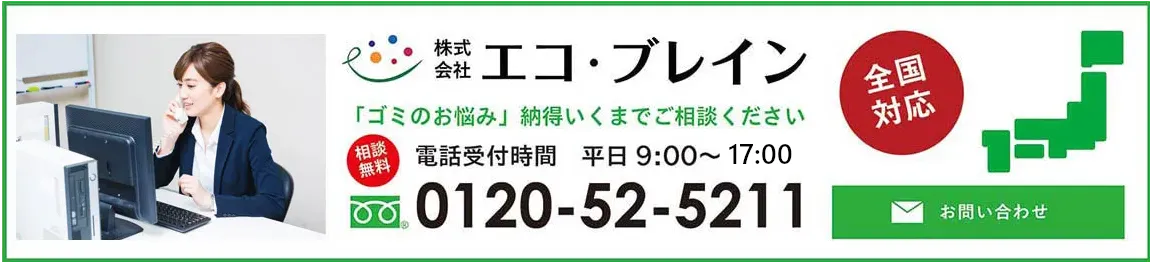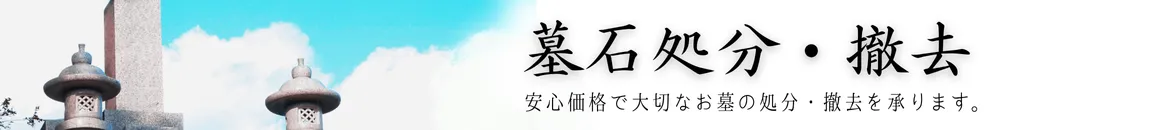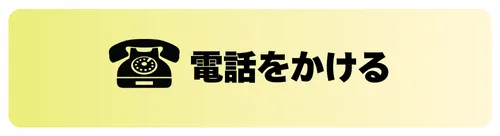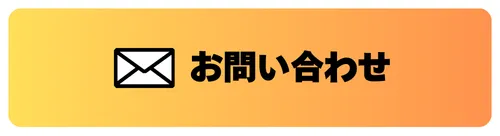廃棄物担当者向け:【特集】主な産業廃棄物の種類と業種別具体例

産業廃棄物は、業種ごとに発生する内容や性状が大きく異なります。
法令では20種類の分類が定められていますが、実際の現場ではそれぞれの事業活動に密接に関係しており、排出の傾向・処理方法・管理体制も多様です。
本記事では、産業廃棄物の主要な種類を分類ごとに詳しく掘り下げるとともに、代表的な業種別の具体例をわかりやすく紹介します。内容は環境省・自治体の公式資料や実務指針に基づいて構成しており、事業者が廃棄物の性状を正しく把握するための参考資料としても活用できます。
1. 法令で定められた20種類の産業廃棄物とは?
産業廃棄物は、廃棄物処理法施行令により明確に定義されており、以下の20種類に分類されます。分類ごとに具体例とともに実務上の注意点を簡単に見ていきましょう。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 燃え殻 | ボイラーや焼却炉の灰。飛灰(フライアッシュ)は重金属を含むこともあり、特別管理産業廃棄物になるケースも。 |
| 汚泥 | 排水処理で発生する泥状物質。含水率が高く処理費がかさむため、脱水や乾燥などの前処理が重要。 |
| 廃油 | 潤滑油や洗浄油、使用済みの調理油。引火性や臭気を持つため保管・運搬には厳重な管理が必要。 |
| 廃酸・廃アルカリ | 化学薬品、酸性・アルカリ性の洗浄液など。腐食性が強く、漏れによる環境リスクが高い。 |
| 廃プラスチック類 | 容器、部品、包装資材など合成樹脂製品全般。発泡スチロール、フィルム材も含む。 |
| 紙くず | 製紙業・印刷業から出る端材やロス紙。オフィスから出る紙ごみは産廃に該当しない点に注意。 |
| 木くず | 建設現場の型枠、パレット、家具など。防腐処理が施されたものは管理型処分が必要な場合も。 |
| 繊維くず | 裁断くず、縫製工場の端材など。天然繊維・化学繊維いずれも対象。 |
| 動植物性残さ | 食肉加工、食品製造の過程で出る肉・魚・野菜くずなど。 |
| 動物系固形不要物 | 骨、皮、内臓など。畜産加工業が主な発生源。 |
| ゴムくず | タイヤ、ゴム製品、ベルト類。天然・合成問わず対象。 |
| 金属くず | 加工工程の端材、スクラップ。鉄・非鉄(銅、アルミ等)ともに再資源化価値が高い。 |
| ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 解体現場や製造時に出る硬質素材。 |
| 鉱さい | 金属精錬後に出るスラグなど。化学性状により分類される。 |
| がれき類 | 建物解体で生じる瓦、れんがなど。粉じん対策が必要。 |
| ばいじん | 集じん装置により回収された微粉末。燃焼工程の副産物。 |
| 動物のふん尿 | 畜産業の排出物。堆肥化などリサイクル活用も。 |
| 動物の死体 | 畜産・研究施設等で発生。感染性の有無により取扱いが異なる。 |
| 13号廃棄物 | その他政令指定の特殊廃棄物(例:複合廃棄物、使用済機器など)。 |
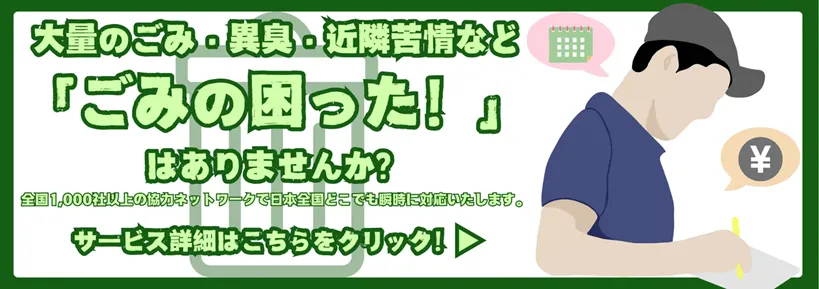
2. 業種別に見る具体的な排出物と傾向
建設業
建設業は、最も多種類かつ大量の産業廃棄物を発生させる業種です。
- がれき類・木くず・金属くず・廃プラ:解体、造成、内装撤去などすべての工程で多様な廃棄物が発生。
- 石膏ボード・断熱材:石綿含有の有無に注意。含有が確認された場合は特別管理産業廃棄物として扱われる。
- 養生シート・梱包材:軽量だが容積がかさみ、適切な保管・圧縮処理が求められる。
現場単位で分別が不十分な場合、混合廃棄物として13号廃棄物になり処分費が高騰するリスクがある。
製造業(機械・化学・金属加工)
製造業では、設備稼働や加工に伴う廃油・金属くず・汚泥の発生が一般的。
- 金属くず:旋盤や切削作業で出る切粉(スラッジ含む)。
- 廃油・廃酸・廃アルカリ:設備の潤滑、薬品の洗浄・反応残渣。
- 汚泥:洗浄水・排水処理の沈殿物。化学処理により有害物を含むケースもある。
- 廃プラスチック類:成型不良品、養生材など。異材混合のままでは再資源化が困難。
加工系の製造業では、切粉への油分付着や化学性状の管理が特に重要。
食品製造業
- 動植物性残さ・廃油:調理屑、揚げ物ラインからの使用済み油。
- 汚泥:食品排水からの有機スラッジ。含有成分により悪臭対策が必要。
- 廃プラ・紙くず:容器包装のロス、搬送資材など。
- 冷凍・加熱施設の清掃廃液:廃酸または廃アルカリに該当。
食品関連では、腐敗や臭気の発生により周辺環境への影響が大きくなるため、迅速な処理体制が重要。
運輸業・倉庫業
- 廃油・汚泥:車両メンテナンス、洗車場の排水施設より。
- ゴムくず・金属くず:タイヤ交換・部品交換にともなう副産物。
- 廃プラスチック類・紙くず:梱包・物流資材の処分にともない発生。
特に大型トラックなどのオイル交換頻度が高く、廃油・ウエス(拭き取り布)などの管理が求められる。
医療・福祉施設(特別管理あり)
- 感染性産業廃棄物:注射針、血液付着物、培養廃棄物など。指定容器による分別・密閉が必須。
- 薬品系廃液(廃酸・廃アルカリ):殺菌剤・試薬残液など。
- ガラスくず:割れたシャーレ・スライドガラス等。
医療廃棄物の誤処理は重大事故につながるため、職員教育・ルールの徹底が不可欠。
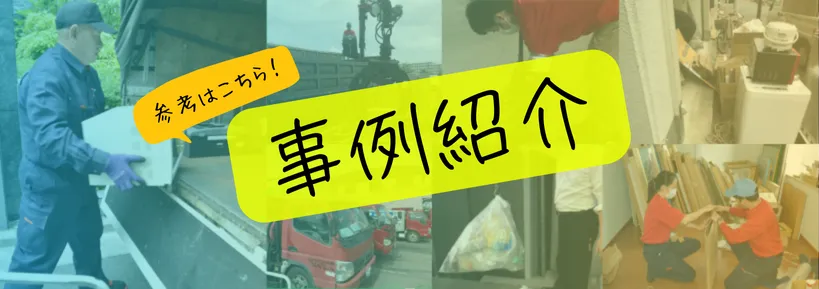
3. よくある誤分類と実務上の注意点
- 事務所の紙ごみ:一般廃棄物。だが、印刷工場から出る紙くずは産業廃棄物に該当。
- 混合廃棄物:分別せずに排出された場合、「13号廃棄物」として扱われ、処理費用が上がる。
- 飲食店の残飯:自治体によっては産業廃棄物(動植物性残さ)とされる。
業種や排出形態により分類が変わるため、自治体ごとのガイドラインや通達の確認が必須です。
また、13号廃棄物に分類されるものは「混合されたままでは処理が困難で、環境負荷が高い」と判断されるものです。特に建設業や物流・解体業などでは注意が必要であり、分別が困難な廃棄物を減らす努力が事業者責任として求められています。
4. 業種別に排出されやすい13号産業廃棄物の具体例
産業廃棄物の分類において「13号廃棄物」とは、前述の19種類に該当しないが政令で定められたものを指し、正式には「政令第2条第4項第20号の産業廃棄物」と定義されています。主に複数の廃棄物が混ざり合って分別困難なもの、または電気機器等で材質・用途が複雑なものなどが含まれます。
以下に、特に排出されやすい業種と13号廃棄物の例を示します。
■ 建設業で多い13号廃棄物の例
建設業では、解体・改修・リフォーム工事などに伴い、混合廃棄物が多く発生します。現場で分別が不十分な場合、それらは13号廃棄物として分類され、通常の廃棄物より処理費用が高額となることもあります。
- 廃石膏ボードと断熱材、木材、ビニールが混ざった内装材の廃棄
- 廃プラスチック類・ゴム・金属片が混在した床材・壁材の解体屑
- 鉄くず・木くず・繊維くずが袋詰めで一体化したもの
- 廃蛍光灯・スイッチボックスなど、材質が混在する電材の解体物
これらの廃棄物は、本来であれば適切に分別することで再資源化の可能性があるにも関わらず、現場での手間や管理体制の不備により混合されてしまうケースが多く見られます。
■ サービス業・倉庫業で見られる13号廃棄物の例
- 大型什器(鉄骨・合板・プラスチックが一体化)を解体した際の廃棄品
- 電子機器・OA機器の分解残材(筐体、ケーブル、基板等の混合)
- 梱包材(段ボール・エアキャップ・緩衝材)の混合廃棄
オフィスや店舗の閉鎖・移転にともなう原状回復工事では、産業廃棄物の種別ごとの分別が難航し、13号に分類される割合が高くなる傾向があります。
■ 排出事業者の責任と対策
13号廃棄物は「分別ができない」ことによって分類されることが多いため、発生段階での「分別可能な廃棄物との識別」「保管方法の工夫」が極めて重要です。廃棄物処理法においても、排出事業者が種類ごとに適切に分別・処理する責務を負うとされています。
また、13号廃棄物は再資源化率が低下するだけでなく、管理型最終処分場での埋立費用が高額になるため、排出コストにも直結します。結果として、「管理が不十分であること」に対する経済的なペナルティとなる側面もあります。
今後は、廃棄物排出を最小限に抑える「設計段階からの廃棄物削減(デザイン・フォー・ディスアセンブリ)」や、「現場分別指導の徹底」「処理業者との連携強化」などが重要な対策となります。
まとめ
産業廃棄物の種類と発生源を正しく理解することは、適正処理と法令順守の第一歩です。特に近年は、処理コストだけでなく、脱炭素・ESG対応の観点からも「廃棄物管理の透明性」が企業評価に直結します。
自社で発生する廃棄物がどの種類に該当するのか、どのように処理されるのかを把握することは、廃棄物リスクを防ぐだけでなく、環境経営の推進にもつながります。まずは実例を参考に、現場からの排出実態を見直すことから始めてみましょう。
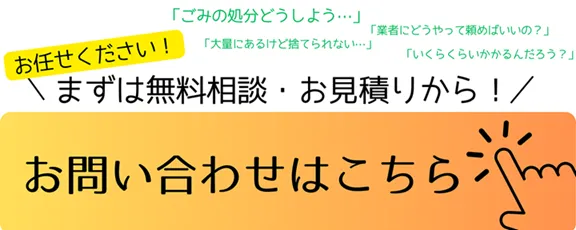
参考・出典:
環境省『感染性廃棄物処理マニュアル(最新版PDF)』
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
環境省『特別管理産業廃棄物の判定基準』
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/
環境省『廃棄物関連ガイドライン(産業廃棄物の判別等)』
https://www.env.go.jp/recycle/waste/guideline.html
環境省『廃棄物実態調査報告書』
https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/
農林水産省『食品リサイクル・食品ロス関連情報』
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/
厚生労働省『医療廃棄物の適正処理指針』
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1543&dataType=1
国土交通省『建設副産物に関する情報』
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/
東京都産業資源循環協会(13号廃棄物関連情報)
https://tosankyo.or.jp/
e-Gov法令検索『廃棄物処理法施行令』
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000300
環境省『中小企業脱炭素経営ハンドブック』
https://www.env.go.jp/content/900440895.pdf
環境省『グリーン・バリューチェーンプラットフォーム(脱炭素経営ツール)』
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/
国連『SDGs目標12|つくる責任・つかう責任』
https://sdgs.un.org/goals/goal12
エコ・ブレインでは、東京23区をはじめ東京都含めた関東圏はもちろん、埼玉県、神奈川県、千葉県、今まで築いてきた全国各地の協力ネットワークもフル活用し、北海道から沖縄まで日本全国が対応エリアとしています。
廃棄物の分別も弊社が行いますので、分別の仕方が分からないという方もご安心ください!
エコ・ブレインの対応地域例
[東京エリア]
中央区、千代田区、文京区、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、豊島区、北区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
[埼玉エリア]
さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)
川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市
狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市
志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市
坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市
[神奈川エリア]
横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、港北区、戸塚区、港南区、旭区、緑区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区、都筑区)
川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区)
相模原市(緑区、中央区、南区)
横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市
大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
[千葉エリア]
千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区、緑区)
銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市
東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市
鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市
南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市
その他上記以外の地域も駆けつけます!
ごみの処分など廃棄物関連にお困りの方、疑問がある方など、ぜひエコ・ブレインまでお問い合わせください!
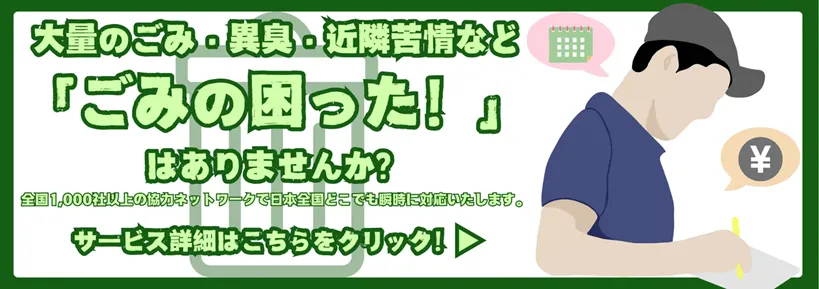
[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案