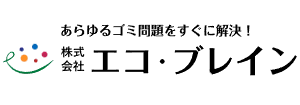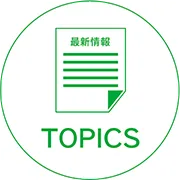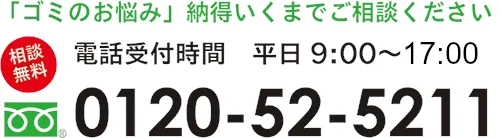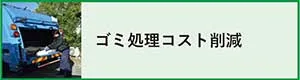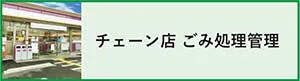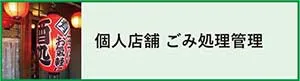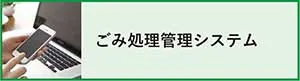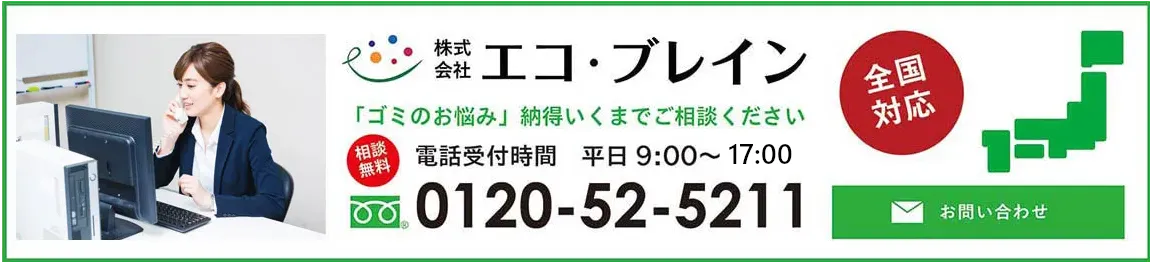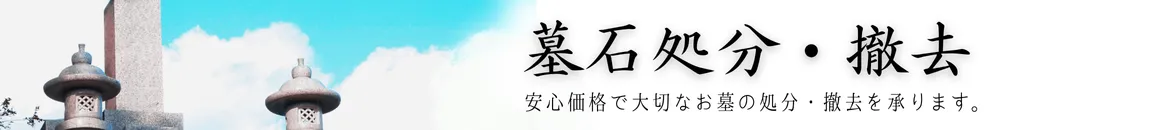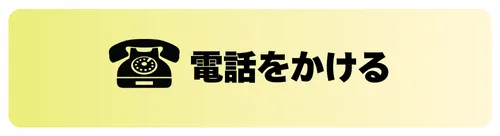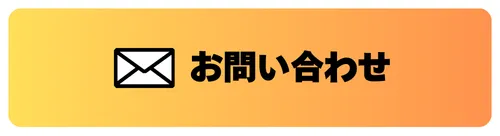火災事故を防ぐために|産業廃棄物処理施設が取るべきリスク対策とは

近年、産業廃棄物処理施設における火事が増加傾向にあり、社会的な関心が高まっています。
廃棄物処理施設内では、日常的に可燃性廃棄物や危険物を扱っていることから、わずかな油断が大きな被害につながりかねません。
この記事では、火災発生の背景やリスク要因、実際の火災事例、被害状況とその社会的影響、そして企業・行政による防火対策とその今後について、幅広く解説します。
火災の背景:産業構造と廃棄物の変化
日本の産業構造が多様化・高度化する中で、廃棄物の種類も従来とは異なる性質を持つものが増えています。とくにリチウムイオン電池のように、高エネルギーで発火性の高い物質が廃棄物に混入するケースが増加し、施設内での火災リスクが急激に高まっています。
家庭や事業所から出るスプレー缶、オイルが染み込んだ紙くず、アルコール類を含む製品など、見た目では危険性が分かりにくい廃棄物が適切に処理されないまま処理工程に投入されると、摩擦や圧力、熱によって容易に発火する恐れがあります。
また、分別の不徹底や排出段階での混入も問題となっており、施設側だけでは完全にコントロールできない側面が火災リスクを増幅させています。
火災の発生状況:実例から見る対応と影響
2025年5月23日午後5時ごろ、東京都大田区城南島にある産業廃棄物処理施設において火災が発生しました。
火元は廃プラスチック処理ラインで、出火原因はリチウムイオン電池によるものとされています。
火災は3日後の5月26日に消防によって鎮火が確認され、幸い人的被害はありませんでした。ただし、施設の一部に物的損害が生じており、関係機関と連携しながら詳細な調査が進められています。
発生当時には煙が広範囲に拡散し、周辺地域への影響も懸念されました。一部報道では、羽田空港周辺で視界への影響が確認され、住民に対しては窓を閉める・不要不急の外出を控えるといった注意喚起が行われたとされています。
この火災の影響により、当該施設での廃棄物受け入れは一時的に停止されており、他施設や協力先による代替対応が実施されています。操業再開の予定については、準備が整い次第、あらためて案内される見込みです。
このような事例は、産業廃棄物処理施設が抱える火災リスクと、それに伴う事業継続や地域社会への影響を再認識するうえで重要な教訓となります。
【参照】
全国の廃棄物管理でお困りの企業様へ
信頼できる業者を探している、処理フローを見直したいなど、
ご相談は全国どこでも無料。まずはお気軽にご相談ください。
処理工程におけるリスクと管理の難しさ
産業廃棄物は、選別・破砕・圧縮・焼却といった複数の工程を経て処理されますが、それぞれの工程において発火リスクが潜んでいます。特に、破砕機やベルトコンベヤーといった大型機械は常に高トルクで動いており、摩擦による火花が発火源になるケースも少なくありません。
また、機械の劣化・摩耗が見逃されたまま稼働を続けた結果、小さな異常が火種になってしまうこともあります。設備の定期点検や温度センサーなどによる監視体制の強化が、火災予防には欠かせません。
さらに、処理工程の自動化が進む一方で、現場の作業員が異常を察知するまでのタイムラグが生じることもリスク要因となっています。
可燃性廃棄物と発火のメカニズム
リチウムイオン電池やスプレー缶は、小型でも非常に高いエネルギーを内包しており、外部からの衝撃・過充電・短絡などがトリガーとなって発火・爆発に至る場合があります。
スプレー缶は内部に高圧ガスを含むため、未使用・未処理のまま破砕機などで圧力を受けると、爆発的な燃焼が発生します。オイルや揮発性液体が廃棄物に付着している場合も同様で、通常よりも低い温度で着火しやすくなることがあります。
施設では、こうした可燃物の混入を防ぐための二重チェック体制や、X線や金属探知機を用いた異物検知が求められます。
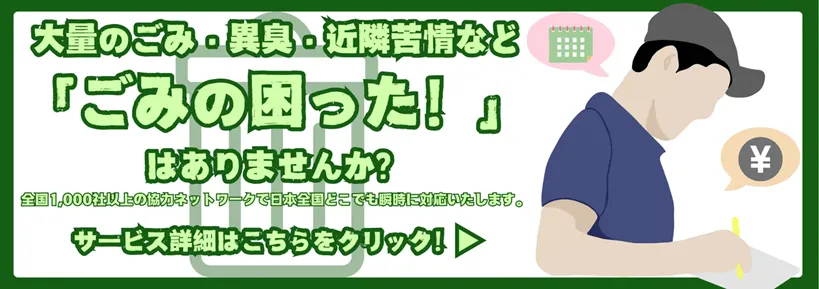
火災発生後の対応と再発防止策
火災が発生した場合、被災施設ではまず被害の最小化を図る初動対応が最重要です。従業員の安全確保を最優先に、初期消火活動や避難誘導を迅速に実施します。その後、関係各所(消防、警察、自治体、取引先)への報告と、原因究明を行います。
再発防止に向けては、以下のような対応が求められます。
- 危険物の受け入れルール見直しと分別マニュアルの再構築
- 安全設備(消火器、報知器、スプリンクラー等)の増設・整備
- 従業員への安全研修と火災訓練の実施
- 監視カメラやIoTセンサーによる異常検知システムの導入
これらの対策を企業の責任で継続的に実行していく姿勢が、信頼回復と再発防止の鍵となります。
法令・ガイドライン遵守の重要性
産業廃棄物処理施設においては、消防法、廃棄物処理法、労働安全衛生法などの関係法令を遵守することが義務付けられています。とくに消防法では、火災危険物を取り扱う事業者に対して、消火設備・避難経路・報知機器の設置など厳格な基準が設けられています。
また、「消防消第15号」などの通知文には、可燃物の保管方法や安全管理体制について、具体的な運用基準が明記されています。これらを無視した運用は、行政処分や刑事責任にも発展しかねないため、施設ごとに管理体制の点検が不可欠です。
実務上の防火対策と日常管理
日常の運営における具体的な防火対策としては、以下のような取り組みが効果的です。
- 可燃性廃棄物と不燃物の明確な分別と区画保管
- 保管上限量の遵守と保管場所の通気・換気
- 毎日の清掃・整理整頓で粉塵や可燃くずの蓄積を防ぐ
- 消火器の定期点検と使用訓練
- 防火管理者の設置と責任分担の明確化
施設運営のあらゆる場面において、「火を出さない」「燃え広がらせない」体制を築いていくことが、総合的な火災予防に直結します。
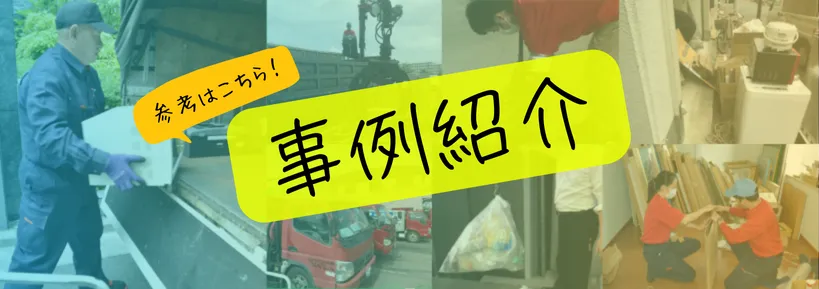
社会全体で取り組むべき課題
火災のリスクは、施設内だけでなく、地域や社会にも大きく影響を及ぼします。そのため、自治体、排出事業者、住民、処理業者が一体となって取り組む姿勢が求められています。
- 自治体:分別指導の強化、火災発生時の情報共有体制の整備
- 排出事業者・住民:リチウム電池やスプレー缶などの適正な分別・排出
- 処理業者:施設側での最終チェックと危険物除去
こうした「排出から処理までの連携体制」が機能することで、火災リスクを社会全体で抑え込むことが可能になります。
まとめ:火災ゼロの実現に向けて
産業廃棄物処理施設の火災は、決して他人事ではありません。ひとたび火災が起きれば、経済的損失だけでなく、人的被害や社会的信用の失墜、地域経済への悪影響など、甚大な被害をもたらします。
そのため、排出・収集・運搬・中間処理・最終処分の各段階で、リスク管理を徹底することが不可欠です。法令遵守に加え、現場での監視体制の強化と、従業員の教育、そして行政・業界との協力体制の確立が、火災ゼロ社会の実現に向けた最短ルートです。
火災を未然に防ぐことは、環境保護にもつながり、廃棄物処理業の健全な発展に直結します。一つ一つの施設の取り組みが、業界全体の安全性と信頼性を底上げしていく原動力になるのです。
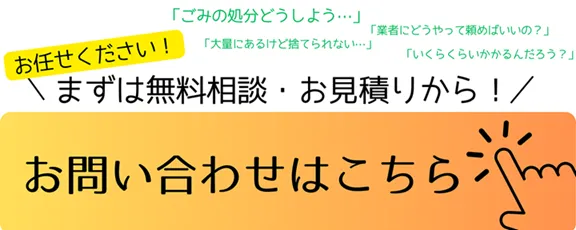
エコ・ブレインでは、東京23区をはじめ東京都含めた関東圏はもちろん、埼玉県、神奈川県、千葉県、今まで築いてきた全国各地の協力ネットワークもフル活用し、北海道から沖縄まで日本全国が対応エリアとしています。
廃棄物の分別も弊社が行いますので、分別の仕方が分からないという方もご安心ください!
エコ・ブレインの対応地域例
[東京エリア]
中央区、千代田区、文京区、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、豊島区、北区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
[埼玉エリア]
さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)
川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市
狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市
志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市
坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市
[神奈川エリア]
横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、港北区、戸塚区、港南区、旭区、緑区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区、都筑区)
川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区)
相模原市(緑区、中央区、南区)
横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市
大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
[千葉エリア]
千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区、緑区)
銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市
東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市
鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市
南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市
その他上記以外の地域も駆けつけます!
ごみの処分など廃棄物関連にお困りの方、疑問がある方など、ぜひエコ・ブレインまでお問い合わせください!
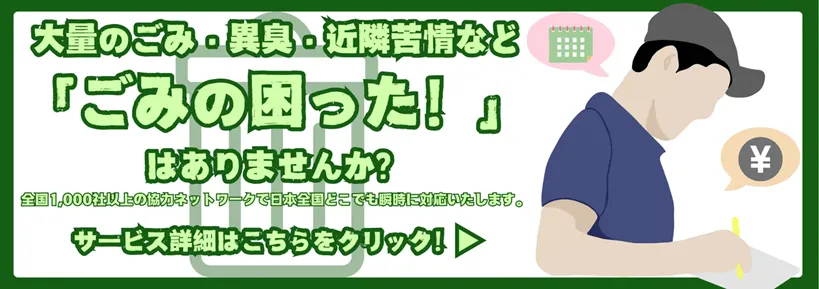
[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案