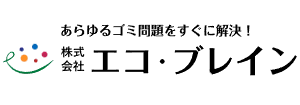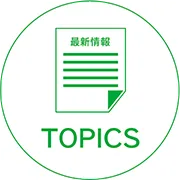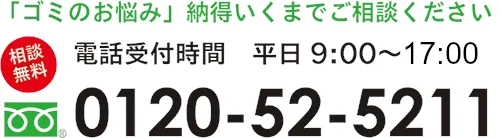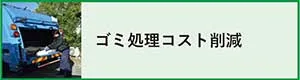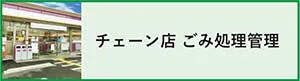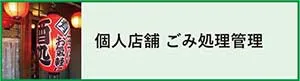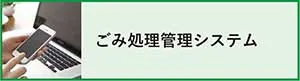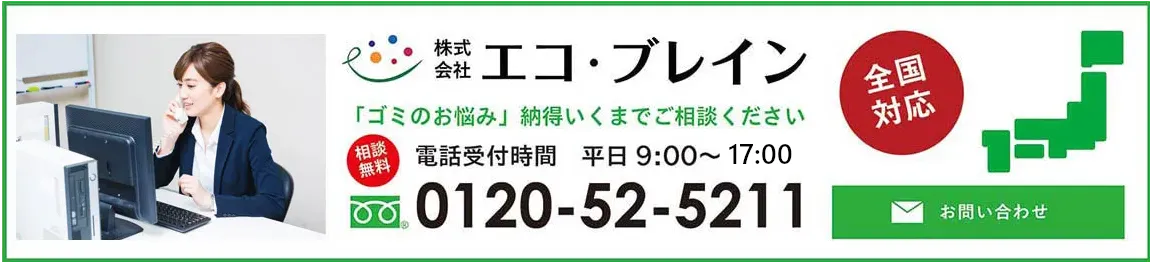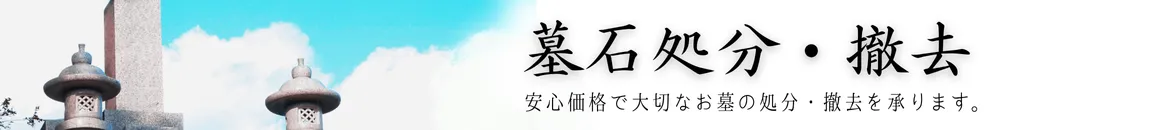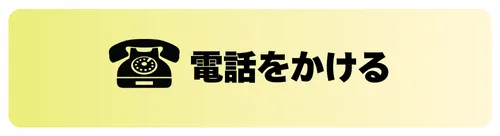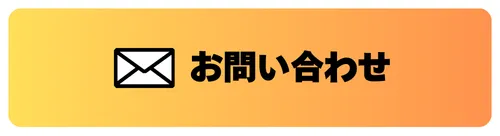産業廃棄物における混合廃棄物の適正処理方法とコスト削減のコツ

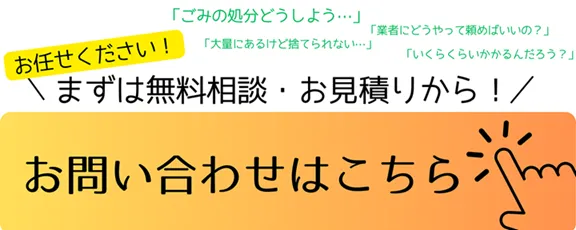
混合廃棄物とは?定義と産業廃棄物との関係
混合廃棄物とは、複数種類の廃棄物が分別されないまま排出された状態のものを指します。特に産業廃棄物の場合、事業活動によって様々な材料が混ざって排出されることが一般的です。
ここで注意すべきは、産業廃棄物と一般廃棄物は法的に区分されており、これらが混在すると違法処理に該当する恐れがあることです。産業廃棄物は事業者が責任をもって適切な処理業者に委託し、マニフェストで管理しなければなりません。
混合廃棄物の主な種類と特徴
混合廃棄物はその性質によって大きく3つに分類されます。
①安定型混合廃棄物
安定型とは、有害物質が溶け出すリスクが低く、埋立処分しても環境負荷が小さいものです。
代表例は以下の通りです。
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ゴムくず
- ガラスくず・陶磁器くず
これらは「安定型最終処分場」で処理されるため、コストも比較的抑えられます。ただし、管理型物質が混入していると受け入れ拒否されるため、事前の分別が必須です。
②管理型混合廃棄物
こちらは環境リスクが高い混合廃棄物です。
- 重金属を含む電子部品
- 塗料付き建材
- 廃油や化学物質が付着した資材
管理型は「管理型最終処分場」で、遮水シートや浸出水処理設備のある施設で厳重に処理されます。処理単価は安定型の2倍以上になることが多く、費用負担が重くなります。
③建設混合廃棄物
解体工事や新築工事など、建設現場で発生する混合廃棄物です。
- コンクリートがら
- 木くず
- ガラス
- 金属くず
- 廃プラスチック類
建設混合廃棄物は安定型と管理型が混在しやすく、処理工程が煩雑になりがちです。工期中に現場内で分別するか、搬出先で分別するかがコストに直結します。
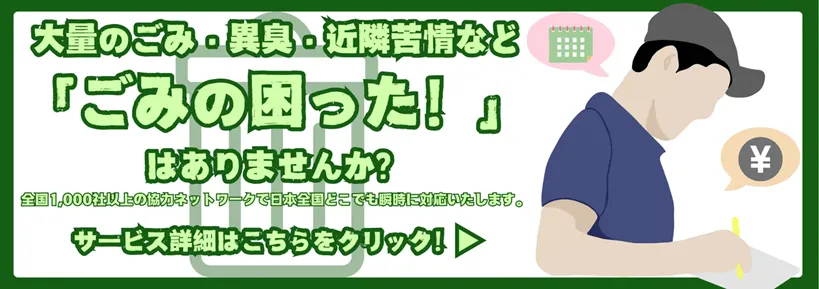
混合廃棄物の適正な処理フロー
混合廃棄物は次の流れで処理されます。
- 排出現場での分別強化
可能な限り現場で分別することで処理コストを大幅に抑えられます。 - 収集運搬
産業廃棄物処理業の「収集運搬業許可」を持つ業者に委託します。 - 中間処理
破砕、選別、焼却などで、最終処分前に適正処理します。 - 最終処分
安定型、管理型それぞれの最終処分場に運ばれ、適切に埋立処理されます。 - マニフェスト管理
排出から最終処分までの流れを電子マニフェストや紙マニフェストで管理します。
混合廃棄物の処理コスト相場と削減策
処理費用は、混合内容や処分方法によって大きく変動します。おおよその相場は以下の通りです。
- 安定型混合廃棄物:8,000~15,000円/㎥
- 管理型混合廃棄物:15,000~30,000円/㎥
- 建設混合廃棄物:内容により10,000~25,000円/㎥
費用を抑えるポイント
- 分別を徹底
リサイクル可能な資源は事前に取り除きましょう。 - 複数業者で相見積もり
処理内容、見積条件をよく比較してください。 - 電子マニフェスト導入
管理コストや事務負担が軽減します。 - リサイクルルートの確保
特に金属くずやプラスチックなどは買取対象になる場合があります。
委託業者選びで失敗しないための注意点
業者選定時には以下を必ず確認してください。
- 都道府県知事の産業廃棄物処理業許可証の有無
安定型・管理型・収集運搬・中間処理それぞれ対応可能か。 - 許可品目に混合廃棄物が含まれているか
- 実績・設備の有無
過去の処理実績や処理フローを確認しましょう。 - マニフェスト管理の対応力
電子対応できるかどうかも評価ポイントです。 - 見積もり明細の透明性
処理工程ごとの費用が明確か確認してください。
混合廃棄物処理における法規制と罰則リスク
混合廃棄物の処理は「廃棄物処理法」で厳格に規制されています。
特に次のような違反は、企業責任が問われます。
- 無許可業者への委託
- 不法投棄
- マニフェスト未提出・虚偽記載
違反時は、数百万円の罰金や営業停止命令が科される場合もあるため、法令遵守は必須です。
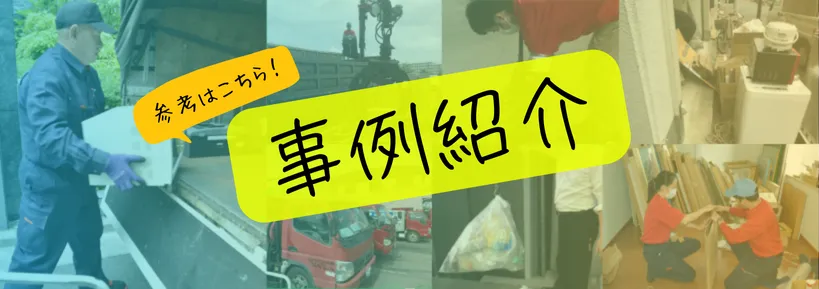
混合廃棄物に関するよくある質問
Q1. 混合廃棄物とは何ですか?
A1.
混合廃棄物とは、複数種類の産業廃棄物が分別されないまま混ざった状態で排出される廃棄物のことです。たとえば「木くず」「金属くず」「プラスチックくず」などが一緒になっている状態が該当します。
法的には「産業廃棄物」に分類されますが、処理の際には適正な分別や中間処理が必要です。
Q2. 混合廃棄物はそのまま廃棄できますか?
A2.
原則として、混合廃棄物はそのまま最終処分することはできません。
廃棄物処理法に基づき、中間処理施設で破砕・選別などの処理を行い、品目ごとに適正処理される必要があります。また、自治体によっては搬入前に分別指導が行われる場合もあります。
Q3. なぜ混合廃棄物は分別しないといけないのですか?
A3.
適正処理やリサイクル促進、最終処分場の負荷軽減のためです。
廃棄物処理法では、排出事業者に「適正分別」の努力義務があります。分別せずに処理を委託すると、処理コストが大幅に高くなる、あるいは受け入れを拒否される場合もあります。
Q4. 混合廃棄物の処分費用は高くなりますか?
A4.
はい、一般的に分別済みの単品廃棄物よりも処分費用が高くなります。
理由は、最終処分前に中間処理施設での選別・破砕などの工程が必要となるためです。大量に発生する場合は、事前分別することでコスト削減につながります。
Q5. 混合廃棄物の排出時に必要な書類はありますか?
A5.
通常の産業廃棄物と同様に、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。
紙マニフェストまたは電子マニフェストのいずれかで管理します。品目欄には「混合廃棄物」「廃プラスチック類・金属くず・木くず等」など、適切に記載しましょう。
Q6. どんな業者に依頼すればよいですか?
A6.
必ず「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」の許可を持つ業者に依頼してください。
特に中間処理(選別・破砕など)が必要なため、「中間処理施設を保有している」または「提携先がある」業者か事前に確認しましょう。
Q7. 混合廃棄物をそのまま埋立できる場合はありますか?
A7.
通常はありません。混合廃棄物はそのまま安定型や管理型最終処分場に直接埋立することは法的に禁止されています。中間処理による適正分別が必須です。
Q8. 混合廃棄物を減らすための社内対策はありますか?
A8.
発生源での分別ルールの徹底、作業員教育、現場内の分別スペース確保が有効です。
まとめ:適切な分別と業者選びが企業リスクを防ぐ
混合廃棄物の処理は、排出段階から計画的に進めることが重要です。
特に、「分別の徹底」「信頼できる許可業者選び」「マニフェスト管理の正確化」は、コスト削減とコンプライアンス対応の両面で効果を発揮します。
適正処理は環境保全だけでなく、企業の信頼維持や将来的なビジネスリスク回避にもつながります。現場担当者や総務部門が一丸となって、確実な廃棄物管理体制を構築しましょう。
エコ・ブレインでは、東京23区をはじめ東京都含めた関東圏はもちろん、埼玉県、神奈川県、千葉県、今まで築いてきた全国各地の協力ネットワークもフル活用し、北海道から沖縄まで日本全国が対応エリアとしています。
廃棄物の分別も弊社が行いますので、分別の仕方が分からないという方もご安心ください!
エコ・ブレインの対応地域例
[東京エリア]
中央区、千代田区、文京区、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、豊島区、北区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
[埼玉エリア]
さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)
川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市
狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市
志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市
坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市
[神奈川エリア]
横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、港北区、戸塚区、港南区、旭区、緑区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区、都筑区)
川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区)
相模原市(緑区、中央区、南区)
横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市
大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
[千葉エリア]
千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区、緑区)
銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市
東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市
鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市
南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市
その他上記以外の地域も駆けつけます!
ごみの処分など廃棄物関連にお困りの方、疑問がある方など、ぜひエコ・ブレインまでお問い合わせください!
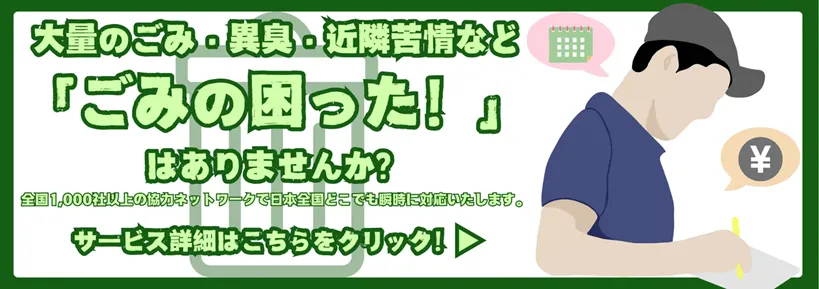
[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案