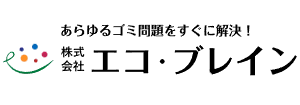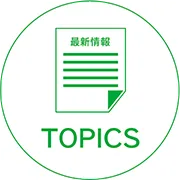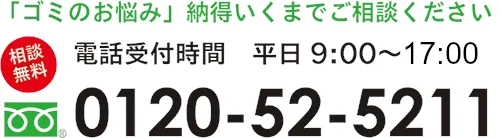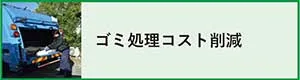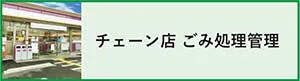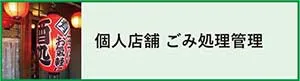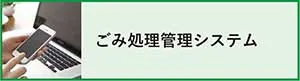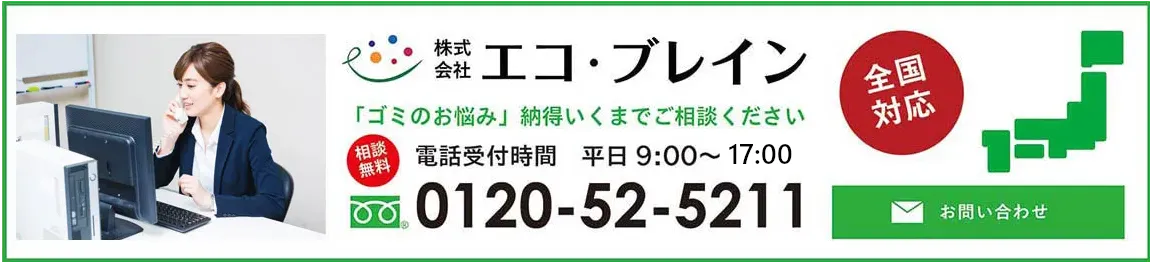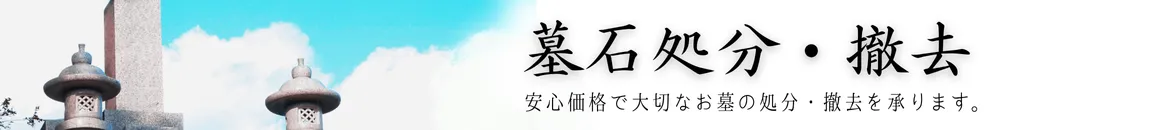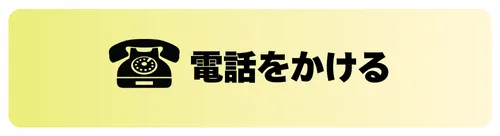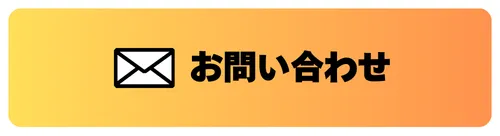廃棄処分品の不正転売を防ぐには?企業が取るべき対策と法的責任

2025年5月13日、声優の小倉唯さんの運営チームが廃棄を依頼していた品の一部が、第三者によってオークションサイトで不正転売されていたことが明らかになりました。現在、法的措置を含む対応が進められており、SNSなどでの憶測投稿に対しても注意喚起が行われています。
参考:「ウマ娘」などの声優小倉唯、廃棄処分品不正転売判明 刑事面対応も視野 憶測情報拡散にも注意
こうした事件は芸能界に限った問題ではなく、あらゆる業種の企業が直面し得るリスクです。廃棄予定の商品が不適切に処理され、流通してしまった場合、企業は消費者の信頼を失うだけでなく、健康被害、風評リスク、そして法的責任まで負う可能性があります。
本記事では、不正転売の実態、関連法令、企業が講じるべき実務的対策について解説します。廃棄物処理の透明性を高め、再流通を防ぐ体制構築に役立ててください。
不正転売とは?再流通によるリスクと企業への影響
不正転売とは、本来廃棄されるべき物品が、第三者によって無断で再販売される行為を指します。対象となる品には賞味期限切れの食品、不良品、試作品、販促物など多岐にわたる物が含まれます。
このような品が正規流通ルートを通らず販売されると、品質保証がなされず、消費者に健康被害や損害を与えるおそれがあります。企業にとっては、社会的信用の失墜や風評被害、損害賠償リスクを招く非常に深刻な問題です。
廃棄物の種類と分類:企業が理解すべき基本知識
廃棄物の適切な処理には、法的な分類を理解することが不可欠です。
- 産業廃棄物:企業活動により発生する廃棄物。排出事業者が最終処分までの責任を負います。
- 事業系一般廃棄物(事業系ごみ):企業や店舗、オフィスなどの事業所から日常的に排出される廃棄物で、産業廃棄物に該当しないもの。多くは市区町村が許可した業者による収集が必要で、家庭ごみとは明確に区別されます。処理責任は排出事業者にあります。
- 一般廃棄物:家庭などから発生するごみが該当します。市区町村が収集・処理を担当します。
- 食品廃棄物:衛生リスクが高く、食品衛生法にも抵触する可能性があるため、特に慎重な管理が求められます。
処分方法や責任範囲が異なるため、分類の誤りが大きな法的リスクにつながることもあります。
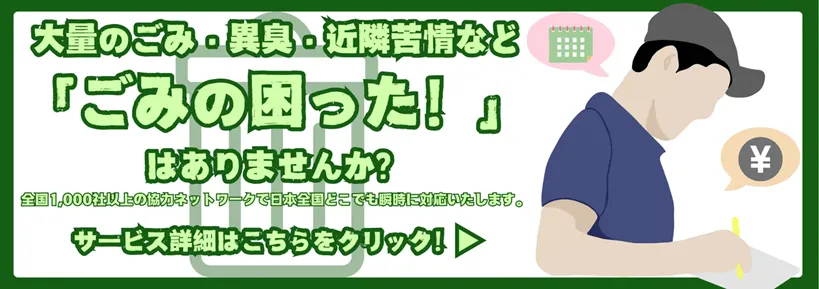
不正転売が起きる背景と誘因
不正転売が発生する主な原因は次のとおりです。
- 管理体制の不備:処分品の数量や流通過程の記録が不十分で、持ち出しや横流しが可能になっている。
- 委託先業者の不適切な処理:委託した廃棄品が適正に処理されず、無断で再販売されるケース。
- 利益目的の第三者の介在:フリマアプリやネットオークションの普及により、一般人でも簡単に販売可能な環境が整っている。
- 社内コンプライアンスの低下:教育不足や内部告発しづらい雰囲気により、従業員の不正が表面化しにくい。
企業が「処分済み」と判断していても、外部委託先や一部の関係者が不正行為に関与している可能性を常に念頭に置くべきです。
実例紹介:廃棄品の不正流通が招いた社会的波紋
近年発覚した不正転売の実例には、企業や著名人が関与する深刻なケースがあります。
2025年には、声優の小倉唯さんの私物が廃棄処分後に第三者によりオークションサイトで転売され、法的措置が取られる事態となりました。
また、カレーチェーン「CoCo壱番屋」で廃棄予定だったビーフカツが、産業廃棄物処理業者「ダイコー」により不正に流通し、スーパーで販売されていた「廃棄カツ不正転売事件」も有名です。この事件では、計108品目の不正転売が確認され、関係者には廃棄物処理法違反や詐欺罪での有罪判決が下されました。
いずれの事例も、委託先の管理不備や価格優先の契約が原因であり、排出事業者にも管理責任が問われました。不正転売を防ぐには、信頼できる処理業者との契約と、処理状況の確認が不可欠です。
法律面から見る不正転売のリスクと企業責任
不正転売に関わる主な法的リスクには以下のものがあります。
- 廃棄物処理法違反:適正な処理を怠った場合、排出事業者も行政処分や罰則の対象に。
- 食品衛生法違反:賞味期限切れや破損品の不正流通は、販売者・排出者双方の責任が問われる可能性があります。
- 詐欺罪・窃盗罪(刑法):意図的に持ち出したり、譲渡目的で不正に取得した場合は刑事事件に発展することも。
なお、これらの適用はケースバイケースであり、違法性や故意の有無などにより捜査・起訴判断が分かれます。企業としては“知らなかった”では済まされない体制の構築が不可欠です。
不正転売を防ぐための実務的対策
1. 廃棄物管理の明確化と記録徹底
- 処分前に写真撮影と数量確認を実施
- マニフェストや引取伝票を保管
2. 社内研修とコンプライアンス教育
- 実際の不正転売事例を教材に使用
- 法令遵守の必要性と個人責任の理解促進
3. 処分委託先の信頼性強化
- 許可・資格の確認、契約条項に罰則明記
- 廃棄後の証拠提示や報告義務の設定
4. ITシステムによる追跡体制の導入
- QRコード・バーコードによる一括管理
- トレーサビリティを確保した監査ログの整備
5. 内部監査・外部通報制度の整備
- 匿名通報窓口の設置
- 第三者監査による透明性の担保
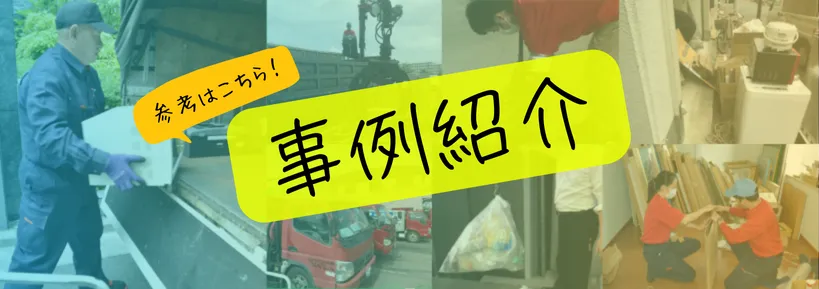
弁護士や専門家との連携の重要性
不正転売が疑われる事案が発生した場合、速やかに弁護士などの専門家に相談することが肝心です。事後対応だけでなく、規定や運用フローの見直しを含め、企業体制の抜本的な整備にもつながります。
また、コンプライアンス専門のコンサルタントや法務チームと連携し、グレーゾーンへの対応方針や予防策を明文化しておくことも重要です。
企業向け:廃棄処分品の不正転売に関するよくある質問
Q1. 廃棄処分を依頼した商品が不正転売されるリスクは本当にあるのでしょうか?
A. はい、実際に発生しています。
たとえば「廃棄カツ不正転売事件」では、CoCo壱番屋が処理を依頼した冷凍ビーフカツが、産廃業者「ダイコー」によって廃棄されず、第三者に転売されていたことが判明しました。処理業者の管理体制が不十分な場合、こうした不正が起こるリスクは現実に存在します。
Q2. 廃棄物の不正転売が発覚した場合、排出事業者に責任はあるのですか?
A. はい、排出事業者には「排出者責任」があります。
たとえ処理を委託していたとしても、契約先の選定・監督が不十分だった場合、企業側にも責任が及ぶ可能性があります。廃棄物処理法では、排出事業者は処分の最終責任を負うとされています。
Q3. 不正転売を防ぐために企業ができる対策はありますか?
A. はい、以下のような多角的な対策が有効です。
- 信頼性のある処理業者の選定(許可・実績・監査結果などを確認)
- 契約書に「転売・再使用禁止」の明記
- マニフェスト制度による処理経路の記録と追跡
- 廃棄品の物理的加工(切断・破砕・マーキング等)
- 処理業者に対する現地確認や抜き打ち監査の実施
Q4. マニフェスト制度だけで不正を完全に防げるのでしょうか?
A. いいえ。
マニフェストは処理の流れを記録するものであり、処理実態の信頼性を完全に担保するものではありません。たとえば、廃棄カツ事件ではマニフェスト上は「処理済み」となっていましたが、実際には廃棄されていませんでした。契約・監査・物理的処理の併用が必要です。
Q5. 不正転売された廃棄品が消費者に届いた場合、企業のブランドイメージはどうなりますか?
A. 企業イメージに深刻な影響を与える可能性があります。
「廃棄されたはずの商品」が市場に出回ると、企業の品質管理や倫理姿勢への信頼が損なわれます。特に食品や医薬品であれば、健康被害に発展するリスクもあり、企業責任が重大視されます。
Q6. 契約書に盛り込むべき文言の例はありますか?
A. はい、以下のような明文化が推奨されます。
「本契約により委託された物品は、廃棄を目的とするものであり、再使用・再販売・譲渡・無断搬出等を一切禁じる。違反が確認された場合には、損害賠償および法的措置を取るものとする。」
このような条項は、違反時の法的対応にも有効です。
Q7. 廃棄カツ事件のような不正転売を見抜くチェックポイントは?
A. 以下のような兆候がある場合は要注意です。
- 相場より極端に安い処理費を提示してくる業者
- 契約内容や処理方法の説明が不明瞭
- 現地確認や施設見学を拒否される
- 処理完了報告や証拠書類が提出されない
- 廃棄前に物理的加工を行っていない
Q8. 万が一、不正転売が発覚した際に企業がすべき対応は?
A. 以下のような迅速な対応が求められます。
- 内部調査の実施と経緯の明確化
- 委託業者への聞き取り・契約書確認
- 消費者・取引先への誠実な説明と対応策の提示
- 必要に応じて法的措置(損害賠償請求・契約解除)
- 再発防止策の策定と社内研修の実施
まとめ:不正転売は防げるリスク
廃棄物の不正転売は、現代の企業にとって決して他人事ではありません。SNSやネットオークションなど、情報と物流が高度に連携した現代では、一度流通してしまえばその影響は即座に拡散します。
企業が不正転売の被害者・加害者の両面に立たされることがないよう、日頃からの管理・教育・監査・契約の整備が求められます。
- 廃棄物の正確な分類と処理
- 処理業者の選定と契約管理
- 不正行為の抑止体制の構築
- 社内外への責任意識の浸透
不正転売は「想定外」ではなく、リスクとして「想定済み」でなければなりません。企業が主体的に対策を講じることこそが、信頼と法令遵守を両立する第一歩です。
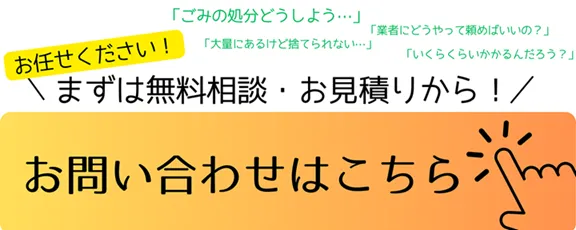
エコ・ブレインでは、東京23区をはじめ東京都含めた関東圏はもちろん、埼玉県、神奈川県、千葉県、今まで築いてきた全国各地の協力ネットワークもフル活用し、北海道から沖縄まで日本全国が対応エリアとしています。
廃棄物の分別も弊社が行いますので、分別の仕方が分からないという方もご安心ください!
エコ・ブレインの対応地域例
[東京エリア]
中央区、千代田区、文京区、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、豊島区、北区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
[埼玉エリア]
さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)
川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市
狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市
志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市
坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市
[神奈川エリア]
横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、港北区、戸塚区、港南区、旭区、緑区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区、都筑区)
川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区)
相模原市(緑区、中央区、南区)
横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市
大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
[千葉エリア]
千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区、緑区)
銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市
東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市
鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市
南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市
その他上記以外の地域も駆けつけます!
ごみの処分など廃棄物関連にお困りの方、疑問がある方など、ぜひエコ・ブレインまでお問い合わせください!
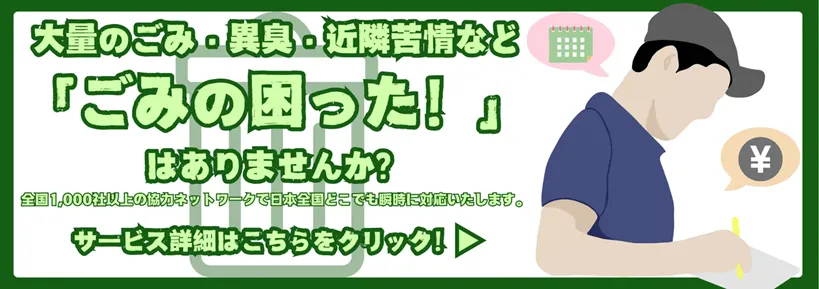
[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案